手術療法
神経芽腫の特徴
神経芽腫という病気は、正常な神経細胞になるはずの芽である細胞「神経芽細胞」が成長の途中で異常に増え始めてできる子どものがんの一つです。このがんは、お腹の中の腎臓の上にある副腎という臓器(図1-1)や、お腹や胸の中にある神経細胞の塊である交感神経節などから発生します(図1-2)。近くにあるリンパ節にも転移しやすく、リンパ節に転移すると最初に出来た元々のがん細胞の塊(原発巣、または原発腫瘍といいます)と一緒になって大きくて硬い塊を作り、身体の中の大事な血管(大動脈やそこから枝分かれして腎臓、腸管、肝臓などを栄養する大事な血管)を取り巻くようにして大きくなって行きます。そして、もっと遠くのリンパ節に転移したり、骨や骨髄に転移することがあるのも神経芽腫が進行していく時の特徴です。それでも、肺や脳にははじめからあまり転移しません。
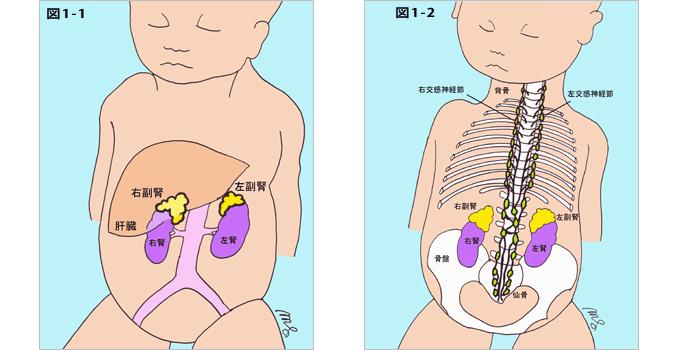
神経芽腫の手術
遠くのリンパ節や骨、骨髄などに転移することを遠隔転移といいます。遠隔転移のない場合の神経芽腫の治療方法としてはまず手術が選ばれますが、遠隔転移がある場合には転移したところをしっかりと抗がん剤で小さくしてからでないと手術をしても余り効果がありません。1970年代までは神経芽腫に良く効く抗がん剤がなかったので、遠隔転移のある場合でもがんが進行するまでにできるだけ早く手術をすることが基本でした。それで神経芽腫の子供たちの多くが遠隔転移を持っていましたが、先に述べたように大血管をぐるりと取り巻く腫瘍でもまず手術を行っていました。抗がん剤で治療をしていない神経芽腫は手術のときにとても出血しやすく、しかも大事な血管はすべて残す必要があるので、小児外科手術の中では難度が高くて長時間を要する手術でした。しかし、このような手術をしても治らないことが多く、骨に転移がある場合はほとんど助かりませんでした。また、遠隔転移がなくて局所に限局している腫瘍では手術で治ることが多いので、原発腫瘍の摘出手術とともにリンパ節の郭清(リンパ節への転移の有無に関わらず周辺のリンパ節も一緒に切除すること)もしばしば行われました。
しかし、最近は抗がん剤による治療の進歩により手術に対する考え方は大きく変わってきています。そして、手術と他の治療方法との組み合わせによってもっとも良い治療成績が得られるように、手術の時期や手術の方法を考えるようになりました。また、神経芽腫の中にはがん細胞の性質によりその悪性の程度が大きく異なり(これを生物学的悪性度といいます)、この生物学的悪性度やがんの拡がりに応じた治療が選択され、手術方法や手術時期が決定されるようになりました。そのために、治療を開始する前に生物学的悪性度を知ることがとても大切で、手術で容易に原発腫瘍が切除できる場合を除いて治療前に下記に説明する生検を行ってがん細胞の性質を見極めるようにしています。
1.生検
生検というのは、がん細胞(神経芽腫)の塊の一部を切除して検査するための組織標本を得ることです。この場合の検査とは、顕微鏡による病理学的検査とがん細胞の遺伝子変化や染色体の異常を調べる検査です。その検査結果により、その腫瘍の生物学的悪性度がわかります。以前はこの生検を行うとがん細胞をまき散らして転移を促進させると恐れられていましたが、現在ではむしろ生物学的悪性度に基づいた治療を行う方が良い結果が得られるために、生検をした方が良いと考えられています。通常の生検の方法は、開腹手術や開胸手術をしてがんの一部を切り取ります。腹腔鏡を使った手術で生検を行う施設や太い針を刺して組織を取る針生検を行う施設もありますが、これらの方法では診断に十分な量の標本が得られず、あまり勧められません。また、我が国では生物学的悪性度を含めた神経芽腫の診断を専門的に行う中央診断システムが構築されています。生検で得られた標本を用いた診断はそれぞれの病院でも行われますが、患者さんやご家族の同意をいただいて中央診断されることにより正確で精密な検査結果が得られ、適切な治療に結びつけることが出来るようにしています。
2.限局性腫瘍
遠隔転移のない腫瘍は限局性腫瘍と呼ばれています。リンパ節に転移があっても、原発腫瘍周囲のリンパ節だけで遠くのリンパ節に転移していない場合はこれに含まれます。限局性腫瘍は一般的に手術で切除出来ますが、原発腫瘍の場所や大きさ、リンパ節転移の仕方によっては手術が難しい場合があります。これまでは、手術で切除出来るかどうかは担当する外科医が判断してきましたが、その判断は客観性に乏しいのが欠点でした。その判断をより客観的に行い、限局性腫瘍に最適な治療法を明らかにするために、全世界で神経芽腫の治療をしている人たちが話し合いをしました。その結果、CT検査やMRI検査などを使った画像診断で手術の困難性をできるだけ客観的に判断する国際的な基準が決定され、この画像診断に基づく危険因子(IDRFといいます)によって手術の難易度を判断することになりました。我が国でもこの判断基準を採用することとなり、「危険因子あり」の場合には初めに生検を行い、その後に抗がん剤による治療を行ってできるだけ危険因子を少なくしてから手術を行います。「危険因子なし」の場合には手術を先に行います。
限局性腫瘍にどのような手術が適切なのかは未だよくわかっていません。そこで、JNBSGでは限局性腫瘍に対しても治療法の検討(臨床試験)を行うことになりました。腫瘍の拡がり、患者さんの年齢、腫瘍組織の生物学的悪性度から治りやすさ(治りにくさでもあります)を決定して治療方法を選択します。いずれにしても限局性腫瘍は、生物学的悪性度が低い場合(神経芽腫のリスク分類の項を参照)には80%以上の子どもが治るので、さらにより良い治療成績を目指しながら出来るだけ合併症が残らない手術方法を選ぶ必要があります。また限局性腫瘍の手術後の抗がん剤治療については、腫瘍の治りやすさによって治療方法を定めています。
2-1. 危険因子(IDRF)を伴わない腫瘍の手術
IDRFがない限局性腫瘍は、それだけおとなしい、言い換えれば生物学的悪性度の低い腫瘍と考えられます。中には治療の必要のない腫瘍もありえます。手術の危険因子がなく手術が可能なので、まず摘出手術を行います。もし腫大したリンパ節があれば、これも一緒に切除します。通常、摘出手術は容易で、大事な血管や臓器を損傷することなしに切除できます。
2-2. 危険因子(IDRF)を伴う腫瘍
初めに生検を行います。その結果によって、神経芽腫リスク分類(JNBSGで定めているがんの治りやすさについての分類)に応じた抗がん剤による術前の治療方法を選択します。術前治療によりIDRFがなくなれば、その時点で原発腫瘍の摘出手術を行います。術前治療によって腫瘍が縮小しても、もともとIDRFのない腫瘍より血管からの剥離が難しいこともあります。また、術前治療をしてもIDRFがなくならない場合も少なくありません。その場合には、規定の治療が終了した時点で手術をします。手術手技や手術方法は外科医に委ねられますが、元来これらの腫瘍は治りやすいことから、手術中や手術後の障害を起こしにくい手術方針が選択されます。腫瘍の被膜が重要な血管に強くひっついているような場合、これを残して切除することも考慮されるべきでしょう。再発した場合にもう一度手術して切除することも可能なので、重要な血管を損傷しないようにすることの方が大事なのです。この点については、今後どのような手術方法が最善かを決める臨床試験を行う必要があると思っています。
3.遠隔転移のある進行神経芽腫の手術
初めに生検を行います。その結果によって先にも述べた神経芽腫リスク分類に応じた抗がん剤による術前の治療方法を選択します。この治療により、90%近い患者さんで原発腫瘍や転移腫瘍の大きさが著しく縮小します。がん遺伝子(MYCN)が増幅した悪性度の高い腫瘍であっても、著しい縮小がみられます。一方、腫瘍の性質によってはあまり小さくならないこともあります。抗がん剤によって縮小した腫瘍は細胞が変化して硬さが硬くなり、出血もしにくくなります。このように術前の治療によって大きさが小さくなったり出血しにくくなることから、一般的には手術はより安全に出来るようになります。しかし、血管からの腫瘍の剥離(剥がすこと)はそんなに簡単ではない場合もあります。手術の考え方には大きく分けて次の二つの方法があります。
3-1. リンパ節の系統的郭清を伴う徹底した手術(図2)
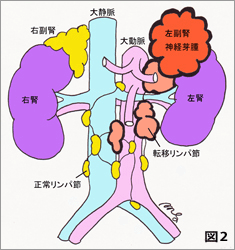
術前に抗がん剤による強力な治療を行って大きさが小さくなった後でも、原発腫瘍や転移リンパ節にまだ生きた腫瘍細胞が残っていることが知られています。そのため、これらの生き残った腫瘍細胞を全部摘出するために、局所のリンパ節を原発腫瘍と一緒に切除しようというのがこれまでの主流の考え方です。この手術では、後腹膜や副腎から発生した腫瘍ではお腹の大血管に沿ってリンパ節転移を起こすので、この大血管に沿ったリンパ節をできるだけ一続きの塊にして切除しようとします。実際にはいくつかの領域に分けて切除せざるを得ないことが普通ですが、血管の周囲には自律神経やリンパ管も取り巻いているのでこれらも一緒に切除することになります。この手術は技術的にもやや難しく、時間もかかります。
そして、手術により大事な血管が攣縮(ぎゅっと縮んで細くなること)することがあり、1歳未満の赤ちゃんなど血管の口径が小さい子どもでは術後に腎臓や腸管の血流が不足して機能が低下することもあります。リンパ管の切り口から大量のリンパ液が長期間にわたってお腹の中に漏れてくることもあります。また、腸管を栄養する血管の近くにある自律神経がリンパ管と共に切除されてしまうので、術後長期間にわたって腸管運動が障害されて下痢や便秘をきたすことがあります。この手術では局所の再発の可能性を少なくする可能性がありますが、手術後の回復が遅れて結果的にその後の治療の開始が遅れたり、治療の継続が難しくなる恐れがあります。
3-2. 原発腫瘍切除と腫大リンパ節のみの切除に留める手術
進行した神経芽腫の中でも遠隔転移のあるものは局所の病気ではなく全身の病気ということになります。そのために、転移先の病巣をも含めた全身の治療をしないと治癒は望めません。そのため、化学療法(抗がん剤による治療)が治療の基本となるので、手術によって治療のスケジュールが大幅に遅れることは望ましくありません。また、系統的リンパ節郭清を行って肉眼的に見える範囲で完全切除を目指しても、どうしても微少ながん細胞は残ってしまいます。そこで、原発巣はできるだけ完全に切除し、血管のまわりにあるリンパ節転移はある程度の大きさのもののみ切除(手術のガイドラインでは2cm以上の大きさのリンパ節または外科医が明らかに生きたがん細胞が残っていると判断したリンパ節)し、手術後の放射線治療と組み合わせてより完璧に近い局所治療を目指そうとするのがこの手術法の考え方です。実際にこの治療を行っている施設では、局所の再発がほとんど抑えられています。この方法の問題は、放射線治療をどの範囲まで行うかということです。この手術法で良い結果が得られるのであれば、手術時間は短縮し、専門施設の小児外科医であればどこでも同じ内容の手術が可能となり、病院の違いによる治療成績のばらつきがより少なくできると思われます。また、術後の治療開始が速やかとなり、治癒した後の後障害もずっと少なくできると思われます。
上記の2つの手術法のどちらが優れているかはまだ明らかではありません。そこでJNBSGでは3-2の方法を原則として施行して、その利点と欠点を明らかにしていく予定です。そして、将来的に必要であれば、どちらの方法が良いかを明らかにする臨床試験を行うことも視野に入れています。
3-3. 手術の時期
進行神経芽腫の治療においては診断後に直ちに腫瘍の摘出手術を行うことはもう行われなくなりました。1980年代に治療効果の高い抗がん剤治療法が開発されると、外科医が手術可能と判断した時期(多くは治療開始後3ヶ月目位)に手術が行われるようになりました。しかし、その時点ではまだ転移先の病巣にがん細胞が生き残っていることが多く、原発腫瘍も縮小過程にあることが多いので、手術時期は次第に遅くなる傾向になりました。やがて、大量化学療法(通常の化学療法で用いる抗がん剤の量に比べ、かなり大量の抗がん剤を投与する治療法)の直前に手術したり、さらには大量化学療法の後に手術を行う施設も出てきました。そこで、JNBSGでは治療開始後4-5ヶ月してから手術する方法と、大量化学療法のあとに放射線治療と組み合わせて手術を行う2つのやり方で臨床試験を行っています。手術方法は主として3-2ですが、施設によりまだ完全に統一されていません。最適な手術時期や手術方法を、臨床試験を通じて明らかにしてゆこうというのがJNBSGの大事な目標です。より安全で確実な手術方法は何かを明らかにして、神経芽腫の治療成績や治療後の生活の質の改善に寄与したいと考えています。



